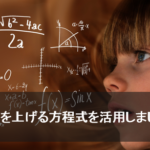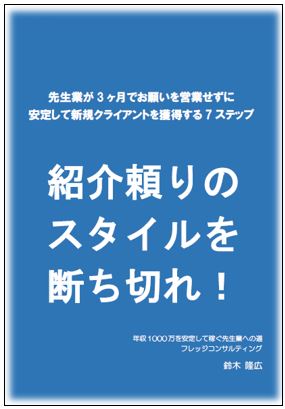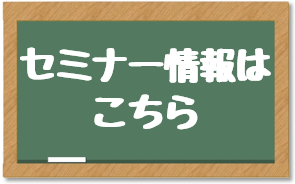ビジネスは基本的に需要と供給で成り立っています。
いくら商品やサービスを供給しても、需要がなければ売れません。
逆に大きな需要があっても、供給されなければ買うことができないのです。
そこで企業はお客さんの欲しいものを掴み、そこに商品やサービスを提供していきます。
では、お客さんが欲しいものはどのようにすれば掴めるのでしょうか?
Contents
お客さんの言う『欲しいもの』は当てにならない

「お客様の声に真摯に耳を傾け、お客様の望みをかなえる」
すばらしい企業姿勢です。
お客さんの欲しいものを売れば当然売れます。
しかし、お客さんは自分の欲しいものが分かっていない場合が多いのです。
どういうことでしょう?
自動車を開発した、ヘンリー・フォードはこう言っています。
「もし顧客に欲しいものを聞いていたら、彼らは『もっと速い馬(馬車)が欲しい』と答えていただろう。」
この場合、お客さんの『欲しいもの』は『もっと速い馬車』です。
つまり、ヘンリー・フォードがお客さんの欲しいものを作っていたら、車ではなく馬車を作っていたかもしれないのです。
しかし、ヘンリー・フォードは結果として車を作りました。
そして、お客さんは「こんな便利な乗り物が欲しかった」と言ったのです。
つまり、ヘンリー・フォードはお客さんが言う『欲しいもの』とは違うものを提供して喜ばれたのです。
お客さんの想像の外にあるものは欲しがれない

車のない時代に、車を欲しいというお客さんはいません。
ましてや馬車しかない時代に、「真っ赤なスポーツカー」を欲しがる人は皆無です。
よく考えれば当然ですが、お客さんは知っているもの・想像できるものの範疇からしか欲しいものは選べないのです。
アップルのスティーブ・ジョブズもそれをこのように表現しています。
「人は形にして見せて貰うまで自分は何が欲しいのかわからないものだ」
アップルのような革新的な商品を生み出す会社だと、このようなことが多数あったのではと予想はつきます。
お客さんの欲求を掴む

では、どうすればお客さんの欲しいもの(想像)以上が提供できるのでしょうか?
ヘンリー・フォードはなぜ『もっと速い馬車』を望まれていた時代に自動車を作れたのでしょうか?
ここにヒントが隠れています。
お客さんの声を無視したのでしょうか?
だとしたら、企業はお客さんの声を無視して、あくまで自分の思うように経営するべきということなのでしょうか?
違います。
フォードはお客さんの『望むもの』を提供したのではありません。
お客さんの『欲求』に応えるものをを提供したのです。
たしかにお客さんは『もっと速い馬車が欲しい』と言っています。
しかし、ここで商品やサービスを提供する側として考えなくてはいけないのは、お客さんは「なぜもっと速い馬車が欲しいのか?」なのです。
お客さんの欲求に焦点を当てて考えると、お客さんの欲求は『もっと速い馬車』ではなく、『もっと早く移動したい』ということが分かるのです。
お客さんの欲求に応えるものを販売する

当時のお客さんの頭には馬車という方法しかありません。
結果として『もっと早く移動したい』という欲求が『もっと速い馬車が欲しい』という言葉に変換されて出てきたにすぎないのです。
つまり、もっと早く移動できるのであれば、馬車である必要は全くないのです。
ヘンリー・フォードは、お客さんのこの『欲求』を掴み、馬車ではなく車を作り上げました。
そして、完成した車をお客さんの前の提示したところ、今まで「もっと速い馬車が欲しい」と言っていたお客さんがこういうのです。
「これが欲しかった」
お客さんの欲求に応える方法は1つではない

これはヘンリー・フォードやアップルに限った話ではありません。
あなたのお客さんもさまざまな悩みや課題や問題を抱えているはずです。
それをその人なりの知識を通した言葉に変換して伝えてきます。
そこであなたが考えなくてはいけないのは「このお客さんは何(物)が欲しいのか?」ではありません。
「このお客さんは何を求めているか(欲求)?」です。
例えば「新幹線に乗りたい」という言葉にダイレクトに応えるとすれば『新幹線に乗る』しかありません。
お客さんの『欲しいもの』に応えられる『もの』は基本的にピンポイントで1つです。
しかし「東京から大阪に行きたい」という欲求に応えるならば、方法は
- 新幹線
- 飛行機
- 自家用車
- バス
- タクシー
- 自転車
- 徒歩
- ヒッチハイク
と、『欲求に応える方法』は無数にあるのです。
無数にある方法を駆使し、お客さんの『欲求に応える方法』を提供するのが専門家であるあなたの役割です。
また、それが本当の意味でお客さんのことを考えると言えるはずです。
まとめ

お客さんは自分の想像の範疇にあるものしか欲しがることはできません。
つまり、そのお客さんにとって本当に欲しいもの、本当に必要なものは、自分では知らない可能性があるのです。
言われたものだけを提供する御用聞きではなく、お客さんの欲求を解消できる新たな提案をすることこそが、真のお客さんの満足へとつながっていくはずです。